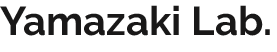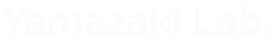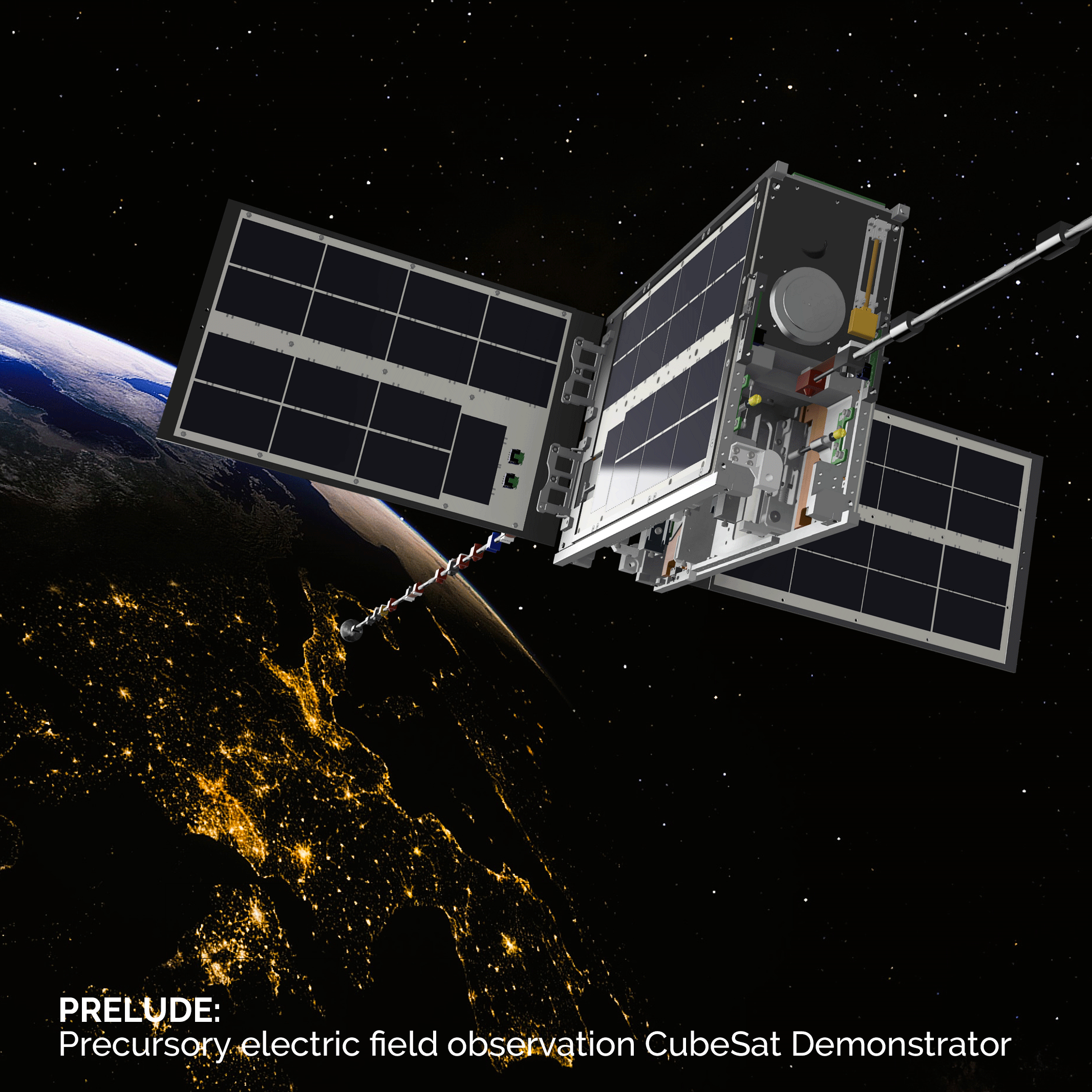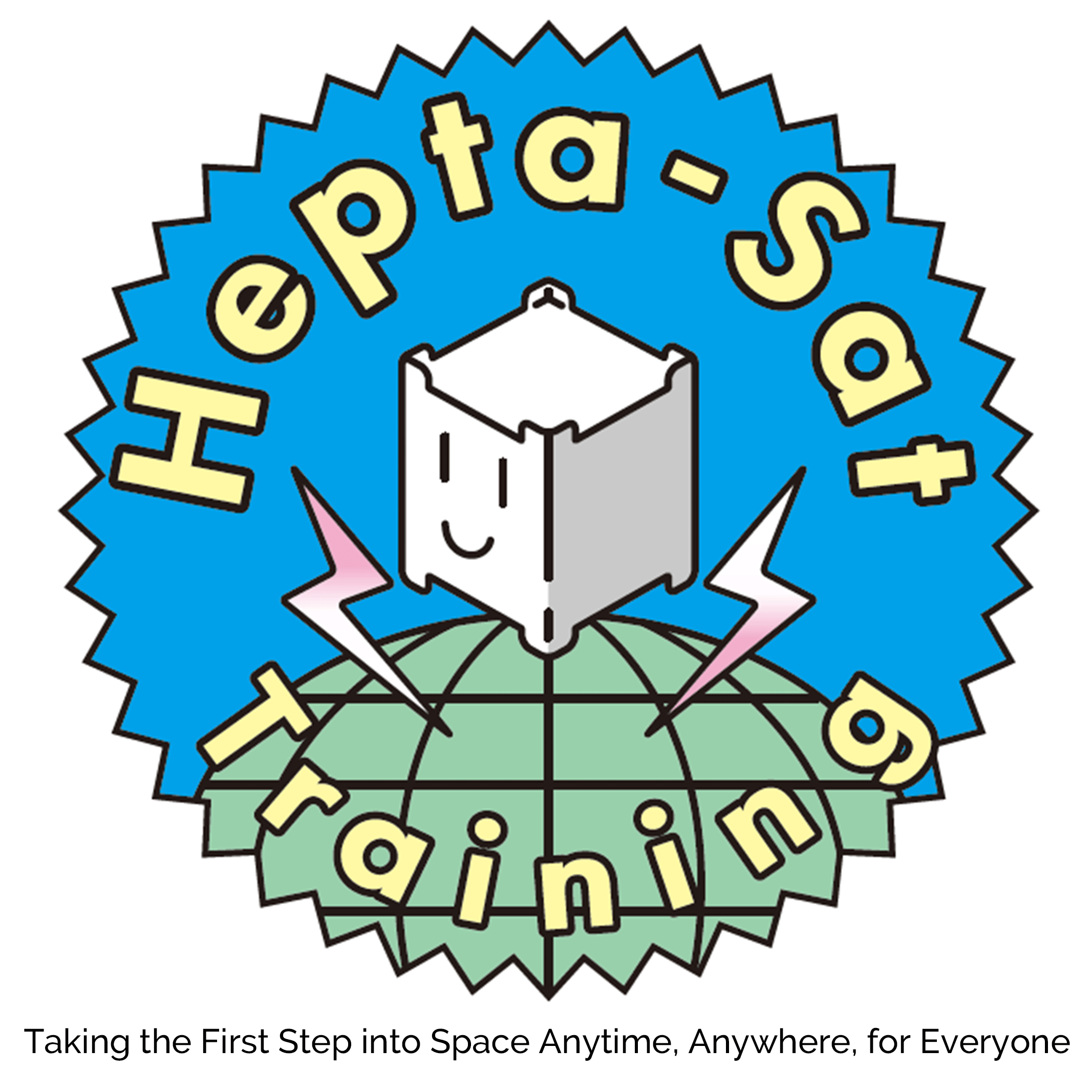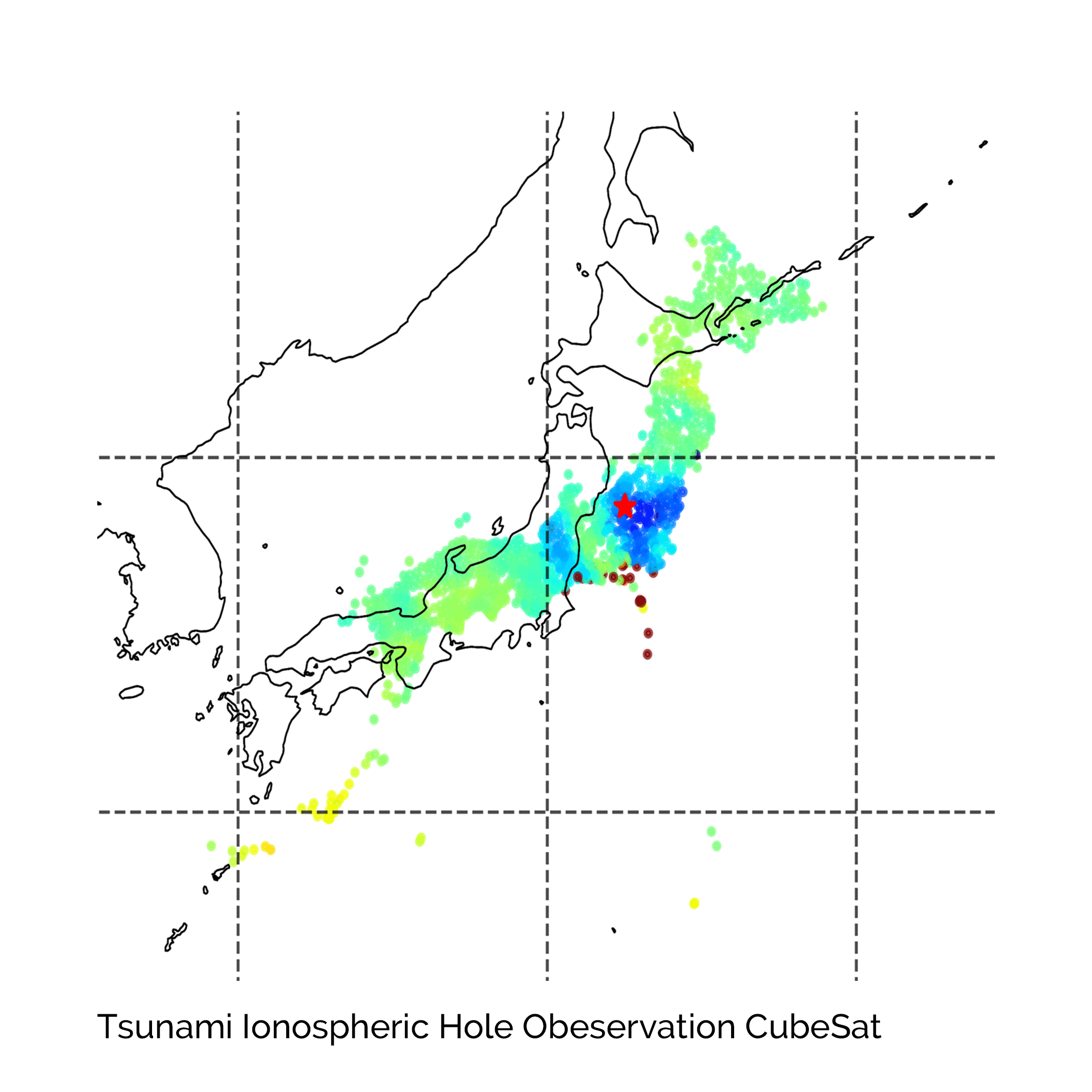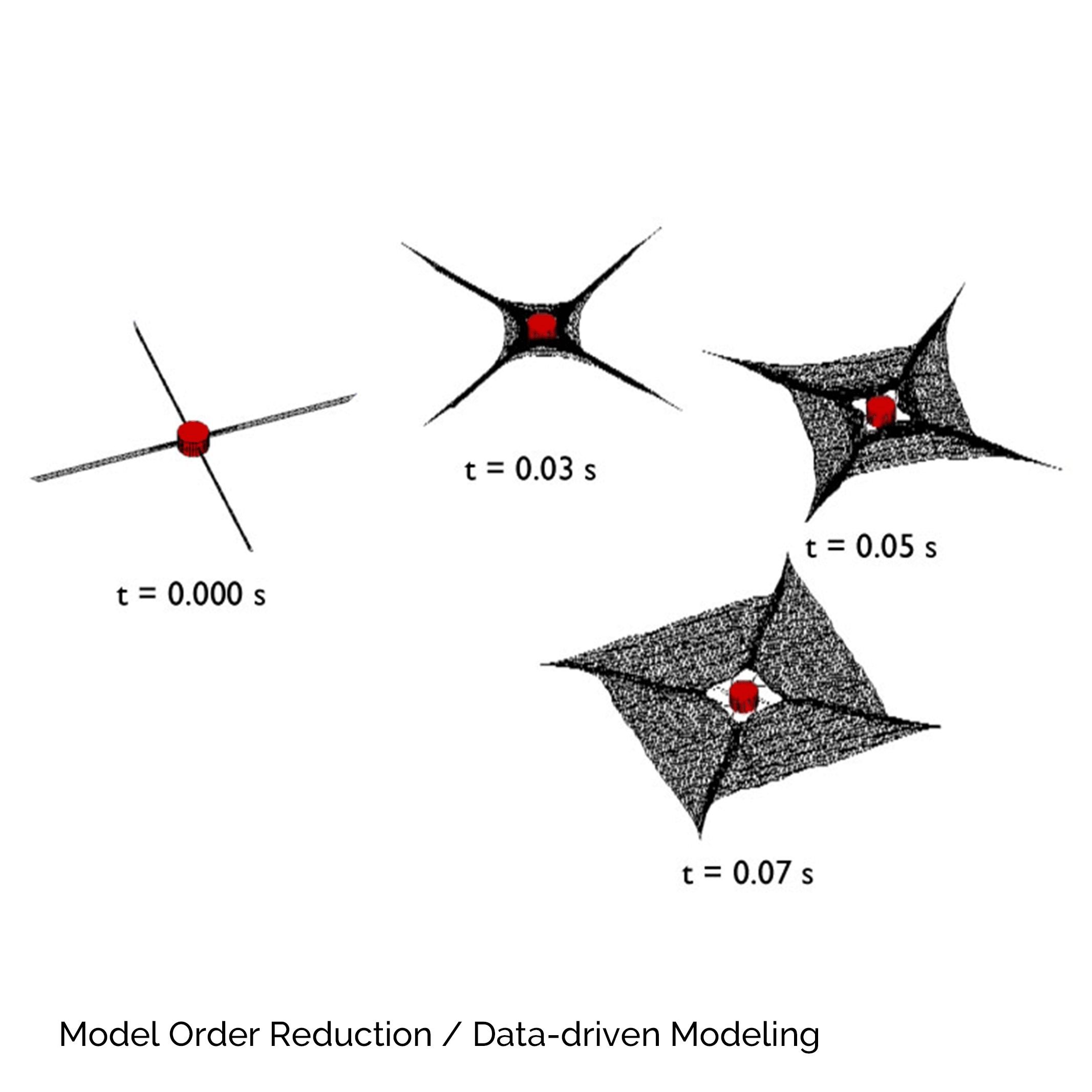Join us as we collaborate with external research institutions in our mission to conduct research related to ultra-small artificial satellites, space structures, space education.
理工学部 航空宇宙工学科 山崎研究室では,学外の研究機関と連携しながら,超小型人工衛星や宇宙構造物,宇宙教育に関連する研究をシステムズエンジニアリング,機械学習,時間・空間情報,ナレッジマネージメントをキーワードに教育・研究を行っています.
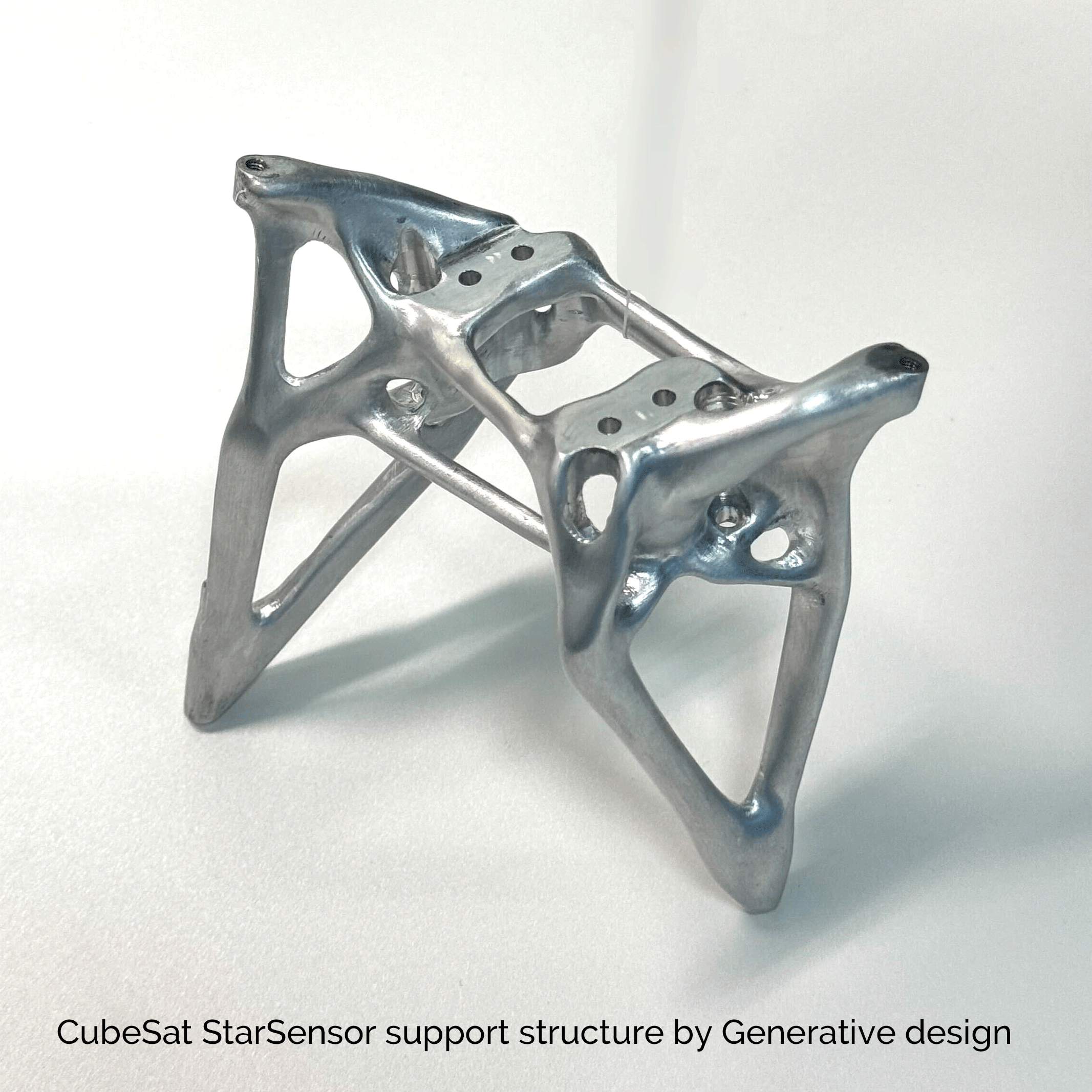
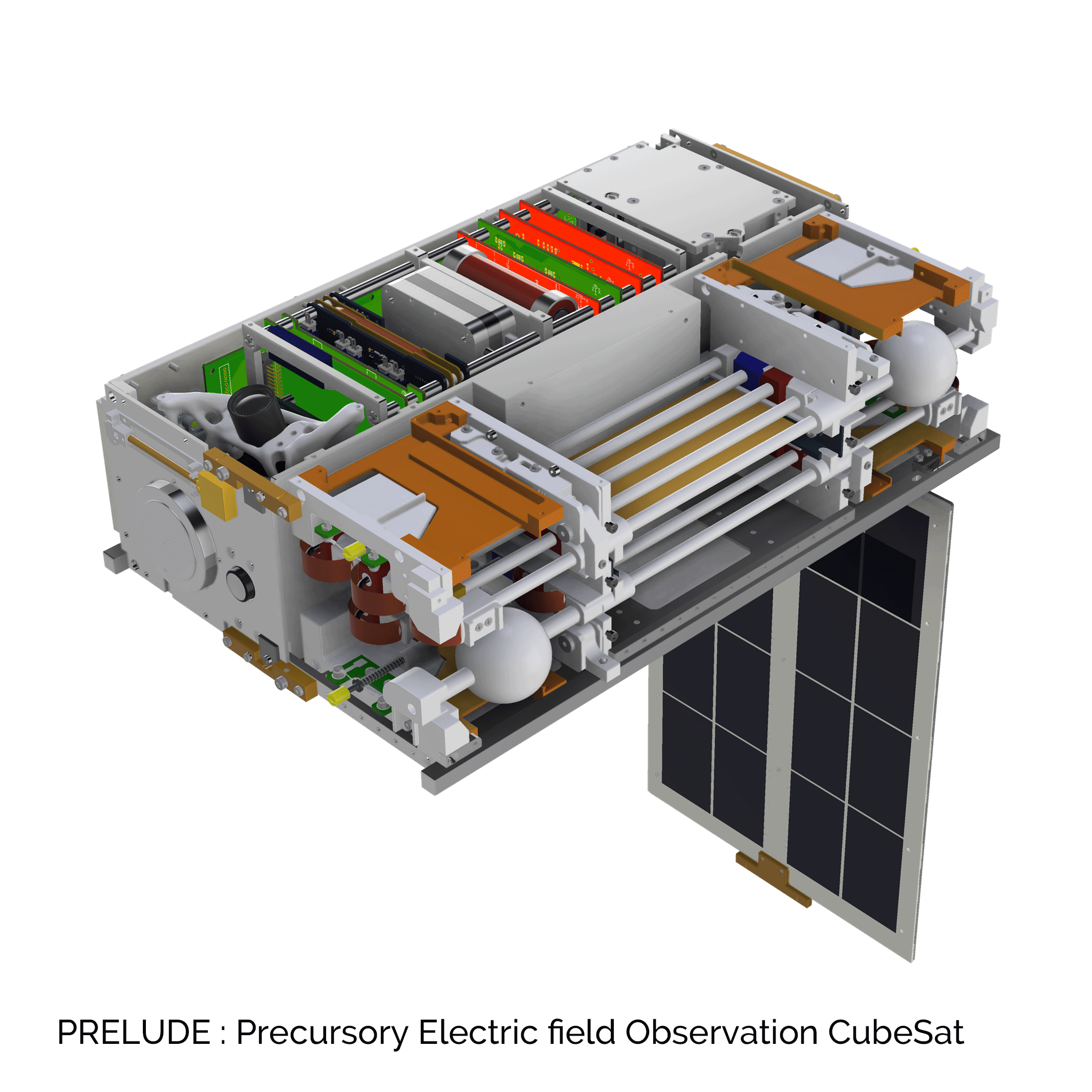
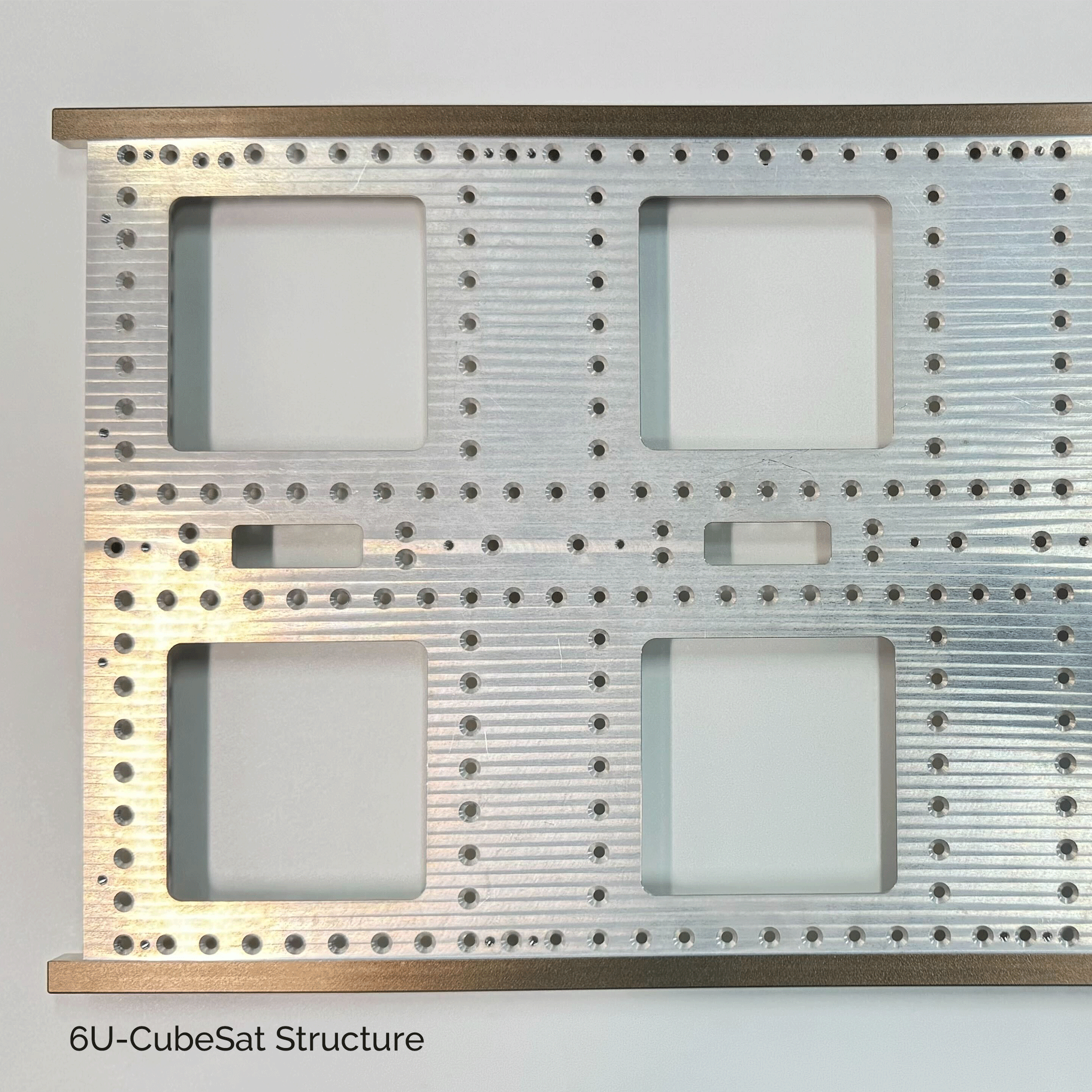
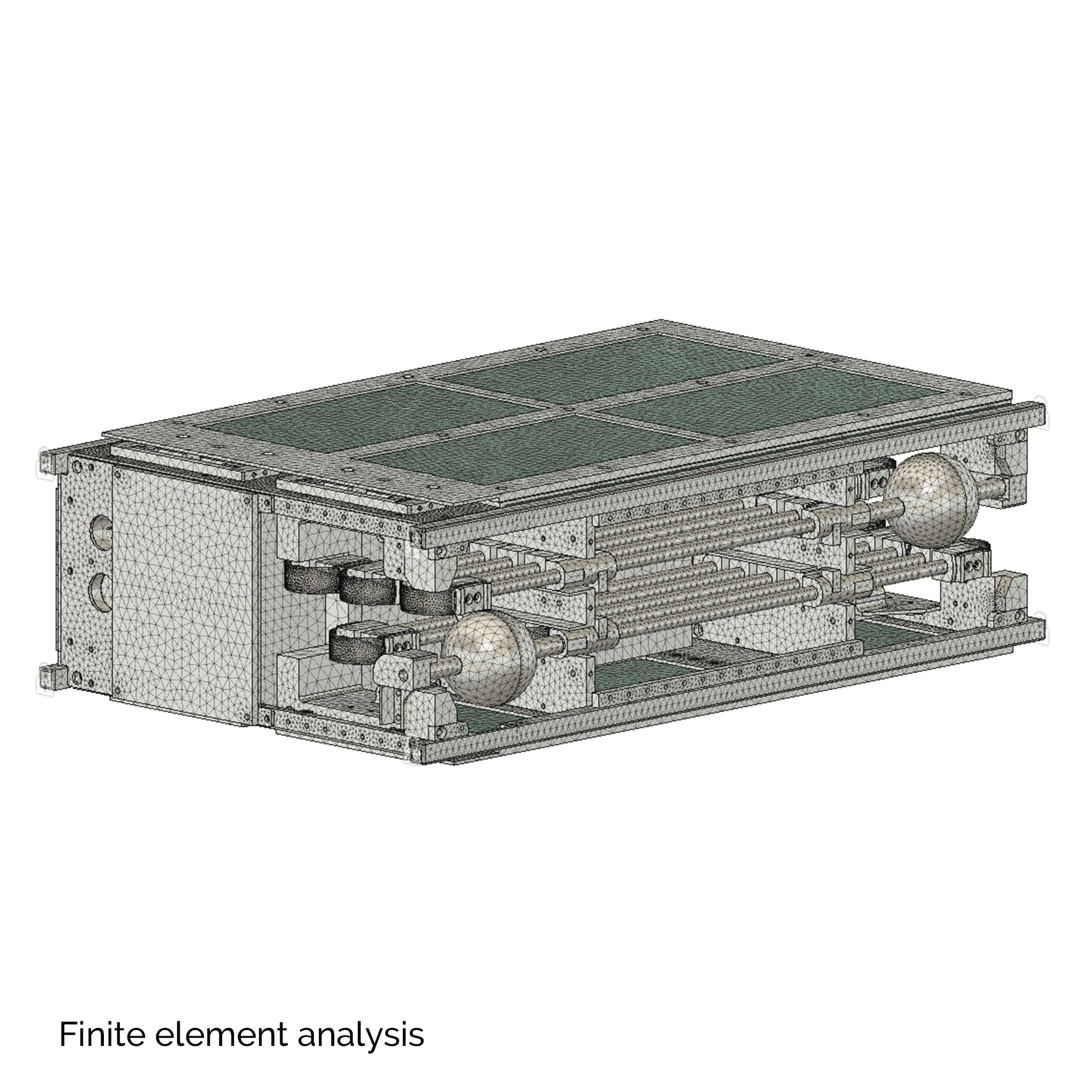
News
8月5-10日に米国で開催された小型の人工衛星に関する国際会議(Small Satellite Conference)で修士課程2年の岩田隆佑君(山崎研究室)が「Model-Based Systems Engineering Education with CubeSat education kit “HEPTA-Sat LITE”」の題目で発表しました.
小型衛星を題材とした宇宙システムの工学教育の可能性を広げるために,衛星機能をワンチップの基板に埋め込み,中高大生や宇宙工学分野以外の人に対して基礎システム工学教育をする手法を提案しました.STEAM教育分野や設計工学分野,今後の宇宙開発の裾野を広げることに貢献する成果です.
本研究では,実際に実機に搭載することを念頭においた観測・データ処理システムのプロトタイプモデルの開発を行う.
統計的有意性が報告されている地震先行電離圏現象の物理機構解明を目指す超小型人工衛星の開発を行っています.先行研究の衛星では部分的にしか得られていない,地震発生と相関があるといわれているVLF帯電波波形データをハイサンプリングで取得し,電離圏(D領域)と呼ばれる領域の観測を目指します.
令和4年11月12日(土)に開催された、「第30回衛星設計コンテスト」最終審査会において、航空宇宙工学科 山﨑政彦研究室と内山賢治研究室の4年生と大学院生合同チームが、「地球電磁気・地球惑星圏学会賞」を受賞しました。
日本大学理工学部は、「稠密衛星観測による早期津波予測システム-NEPTUNE-」というテーマで、設計の部の最終審査3チームに選ばれており、プレゼンテーションをし、受賞となりました。
「稠密衛星観測による早期津波予測システム-NEPTUNE-」は、津波流速観測(AIS)、津波水位観測(GNSS-R)、津波電離圏ホール観測(GNSS-RO,Impedance probe)の3つの手法を求めることによって予測誤差が少ないシステムを目指しています。
理工学部の記事はこちら.
第8回国際超小型衛星ミッションアイディアコンテストにて,航空宇宙工学科山崎研究室と静岡県立大学が共同で提案した,”CubeSat-Constellation-Based Global Early Warning Tsunami Forecasting”がIAA賞(International Academy of Astronautics)を受賞いたしました.
当日の様子はこちらです.
超小型衛星の開発を単一プラットフォームで、ジェネレーティブデザインや金属3Dプリンタも活用する件に関してMONOist様に取材いただきました.記事本分はこちら.
Mission
1
地球規模課題に関する宇宙システム
地震や津波などの地球規模の変化を宇宙から観測することが期待されています.宇宙から捉えた現象を生かした社会システムの創造に貢献することを目指します.
2
大規模システム構築に関する設計言語
現在の社会では,複雑性や不確実さ,価値の多様性が高まり,問題解決が望まれる領域は,混沌かつ曖昧としています.新たなシステムによって問題を解決するにあたり,問題を構造表現として整形する方法の構築に挑みます.
3
俯瞰的な視点でモノを見る学びの場
身の回りから宇宙規模までの対象を含めたシステムのデザインを思考することで俯瞰的に物事を捉える人材を育む教育システムの構築に挑みます.
現在の状況
2020年4月に発足し,活動を開始しています.現在は日本大学理工学部航空宇宙工学科の修士2年生4名,修士1年生4名,学部4年生6名を学生メンバーとして活動しています.プロジェクトや研究毎に他機関の方々と連携しながら進めています.(Jul. 2024)
山﨑は現在,NPO法人大学宇宙工学コンソーシアムでも理事としても実践的工学教育活動の普及に関連した活動をしています.
普段の研究室の様子はここから少し覗けます.
Research and Projecs
― 地震に先行する電離圏の変動現象を観測する超小型衛星PRELUDEを静岡県立大学と共同で開発しています.
― We are jointly developing a microsatellite called PRELUDE in collaboration with Shizuoka Prefectural University to observe ionospheric variations preceding earthquakes.
― 宇宙への一歩をいつでも,どこでも,誰にでも.多様なバッグラウンドの人と宇宙を繋げるための体験型衛星教材HEPTA-Sat(ヘプタサット)を開発しています.
―We’re developing HEPTA-Sat, an experiential satellite education kit, to make the first step into space accessible anytime, anywhere, and to everyone, connecting diverse backgrounds to the cosmos.
― 津波の波源を宇宙から直接捉えることが可能な早期津波予測技術実証衛星群の設計に,静岡県立大学の鴨川仁先生と取り組んでいます.
―We are collaborating with Dr. Masashi Kamogawa from University of Shizuoka on the design of a constellation of technology demonstration satellites aimed at the direct observation of tsunami wave sources from space for early tsunami prediction.
― 膜面宇宙構造物の展開・展張ダイナミクスの解析に力学構造を保存するデータ駆動型モデルを適用し,解析時間の削減やダイナミクスの推定を行う研究です.
―We proposed research findings using a data-driven model that preserves mechanical structures, focusing on both the reduction of simulation time and the estimation of dynamics in the deployment and extension of membrane space structures.
― 開発の初期段階における重要な部分であるシステム化領域の構造化に焦点を当て,システム完成後の致命的不具合の未然防止を目指せるシステム設計・開発手法を考案し,実機開発へ適用・評価を行う.